
「またSNS特定班が即特定してる……」
炎上した“シュシュ女”の情報がネット上で一気に特定された件が波紋を広げています。
顔写真、インスタ、勤務先までが短時間で暴かれ、「SNSの怖さ」を改めて実感した人も多いのではないでしょうか。
なぜここまで早く特定されるのか? 背景には“SNS特定班”と呼ばれるユーザーたちの驚くべき手口と、ネット社会ならではの心理が潜んでいます。
この記事では、シュシュ女の即特定に至った流れと、炎上と特定が拡散する仕組みなどを徹底解説。
自分自身が“特定される側”にならないための対策についてもお届けします。
目次
シュシュ女は何をした?
たけし、シュシュ女が話題らしいよ。韓流アイドルグループZEROBASEONEのお見送りイベントでの対応が悪かったみたいだね。見比べるとたしかにって感じだよ。
pic.twitter.com/rttdVtAjSs— しごできジャイアンの母ちゃん (@iiGIANTmom) May 12, 2025
シュシュ女と呼ばれる女性は、アイドルグループZEROBASEONE(ゼベワン)のミーグリ(Meet & Greet)の女性スタッフ。
お見送り会の際、時間管理のために客を誘導するいわゆる「剥がし」担当でした。
剥がしのやり方が荒く速すぎで、しかもその女性スタッフは笑っている、との理由で炎上、SNSで大バッシングが始まったのです。
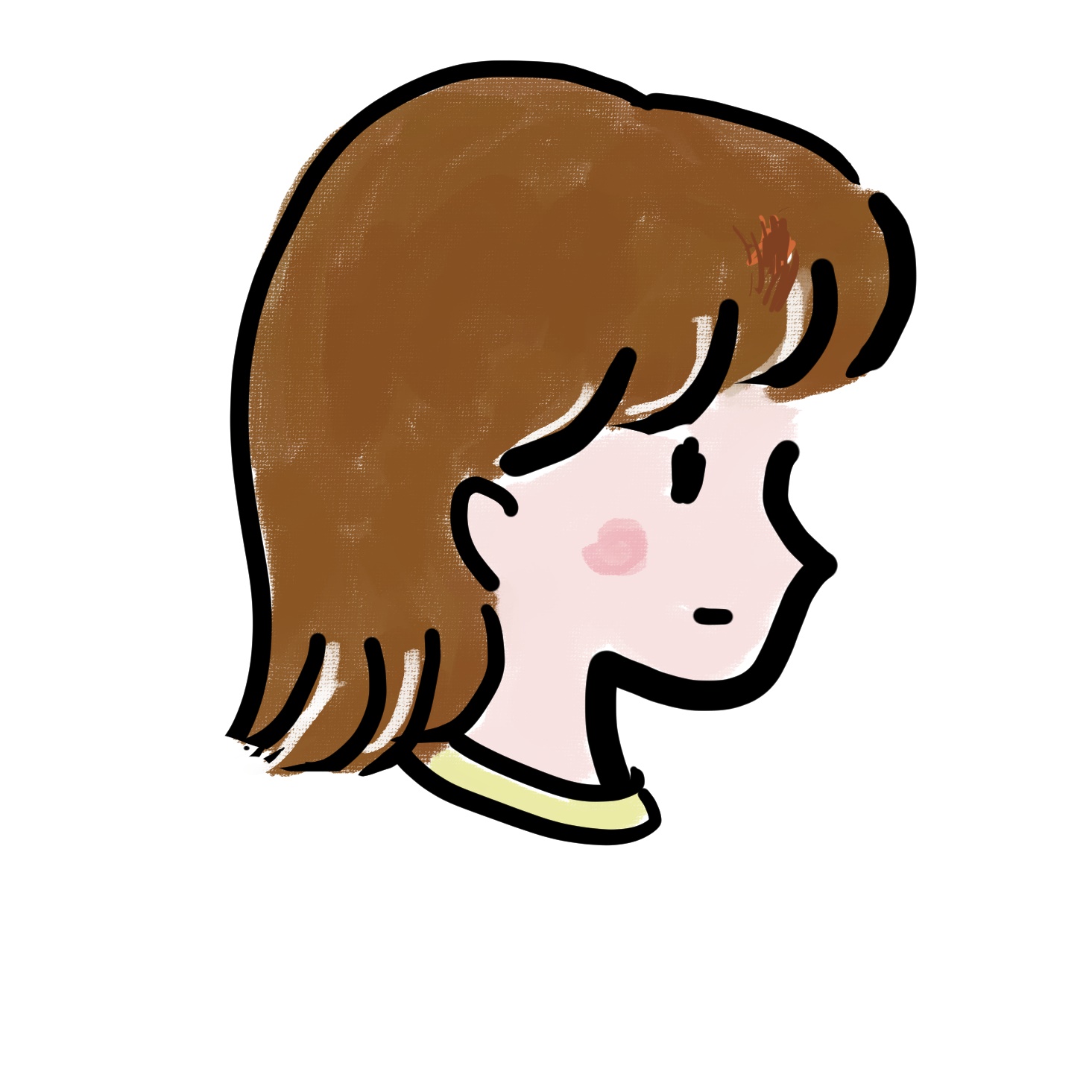
この女性スタッフは髪を後ろで束ね、白いシュシュをつけていたのでSNS上で「シュシュ女」「シュシュネキ」と呼ばれています。
シュシュ女が炎上直後に即特定された理由
“シュシュ女”が炎上したのは一瞬の出来事でしたが、衝撃だったのが「特定」されたスピードです。
ネット上では、彼女の顔写真からインスタアカウント、勤務先の情報までもが、数時間以内に特定され、拡散されていきました。
この背景には、SNSに日々蓄積されている膨大な個人情報の存在があります。
過去の投稿履歴や、写真に映り込んだ背景、持ち物、服装、アクセサリーといった“ヒント”が、特定の糸口になるのです。
とくにX(旧Twitter)やTikTokでは、同じアイテムを身につけた過去の投稿が見つかったり、「背景の場所が〇〇公園では?」といった情報が連鎖的に発掘されたりします。
まさに“ネット上の監視カメラ”とも言える仕組みです。SNS特定班の手口は、想像以上に緻密で、執念深くなっています。
シュシュ女の顔とか名前晒したり顔バカにするのはちゃうやろ
— らーゆ (@GUNSIN_GUNSIN) May 12, 2025
シュシュ女さん1日で人生終了で怖い
たった半日ほどで顔もインスタも特定されるのまじでオタクで探偵事務所とか作った方がいい— もめん (@pudding___07) May 11, 2025
シュシュ女さんかわいそうや
男性アイドルなんだからスタッフも男性にすればいいのに— あ (@0TtMHiNob393752) May 12, 2025
SNS特定班の手口が加速する背景とは?
“特定班”の活発化には、現代特有の背景があります。
ひとつは、SNS上で「私刑」が正当化されやすい風潮です。
シュシュ女の場合も、「アイドルに迷惑をかけた」「非常識な振る舞い」といった怒りが、即特定への勢いを加速させました。
さらに、ネット上では「特定に成功した人」が称賛される傾向があります。「すごい!」「よく見つけた!」といったリアクションが、特定行為そのものを“ゲーム”のように感じさせるのです。
この「承認欲求の代理満足」は、特定班の原動力にもなっています。
また、多くのユーザーがSNSの設定を甘くしている現実も見逃せません。
同じユーザー名を複数のSNSで使っていたり、鍵をかけずに投稿していたりすることで、情報が簡単に紐づけられるのです。
こうした“油断”が、特定班にとっては格好のターゲットになります。
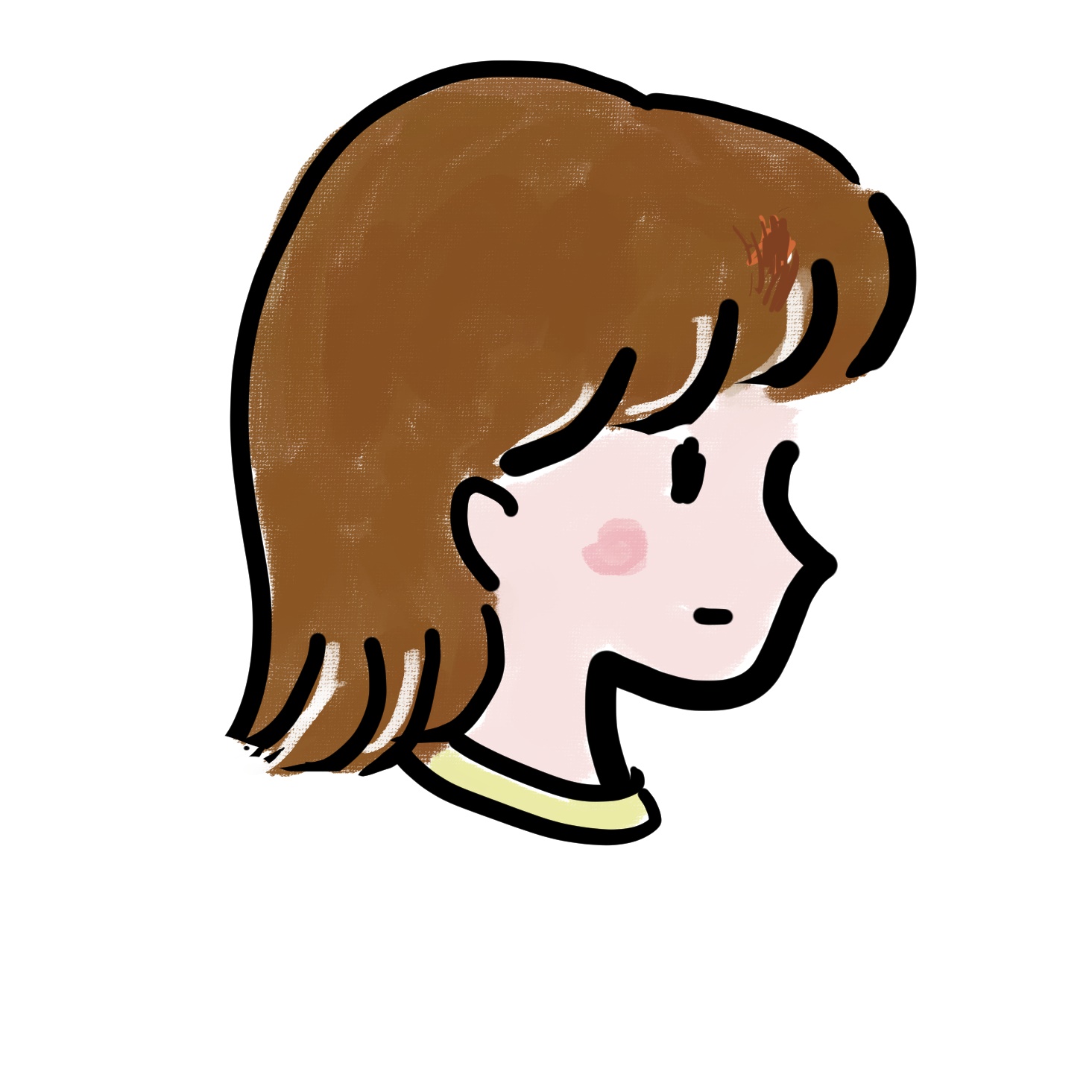
炎上と特定が“正義”になるSNS時代の心理
「晒されて当然」という声が飛び交うSNS社会では、正義とエンタメが混ざり合った危うさがあります。
シュシュ女のように、ネット上で“悪者”認定された人物が特定されると、多くの人が拍手喝采するような状況が生まれるのです。
しかし、その裏側では、正義という名の“ストレス解消”が行われているケースも多いといえます。
失敗した人を叩き、吊るし上げることで、日々のモヤモヤを晴らしている——そんな心理が見え隠れしています。
「ちょっとスカッとした」「ざまあみろと思ってしまった」……そんな気持ちを抱いたことはありませんか?
これは、正義感と娯楽が曖昧になる“特定文化”ならではの問題です。
正しさを盾に、人を傷つけてしまっているかもしれないことに、私たちはもっと自覚的になる必要があります。

あなたも即特定されるリスクと“油断”の怖さ
「私は目立つことしてないから大丈夫」——そう思っていても、今のSNS時代では油断が命取りです。
何気ない投稿、背景に写った場所、服装、つながりのあるフォロワーなど、あらゆる要素が即特定の材料になり得ます。
今回のシュシュ女も、数件の目撃情報とインスタの投稿がきっかけで、短時間のうちに素性を特定されました。
彼女が問題行動を取ったかどうかは別として、こうした“情報の連鎖”が一般人にも簡単に及ぶことが、今のネット社会の怖さです。
特定されるリスクは、誰にでもあります。
正義感から特定に関わることもあるかもしれませんが、それが誰かの人生を壊す行為になってしまっていないか、一度立ち止まって考えることが大切です。
“見ている側”と“見られる側”の境界線は、思っているよりずっと薄いのです。
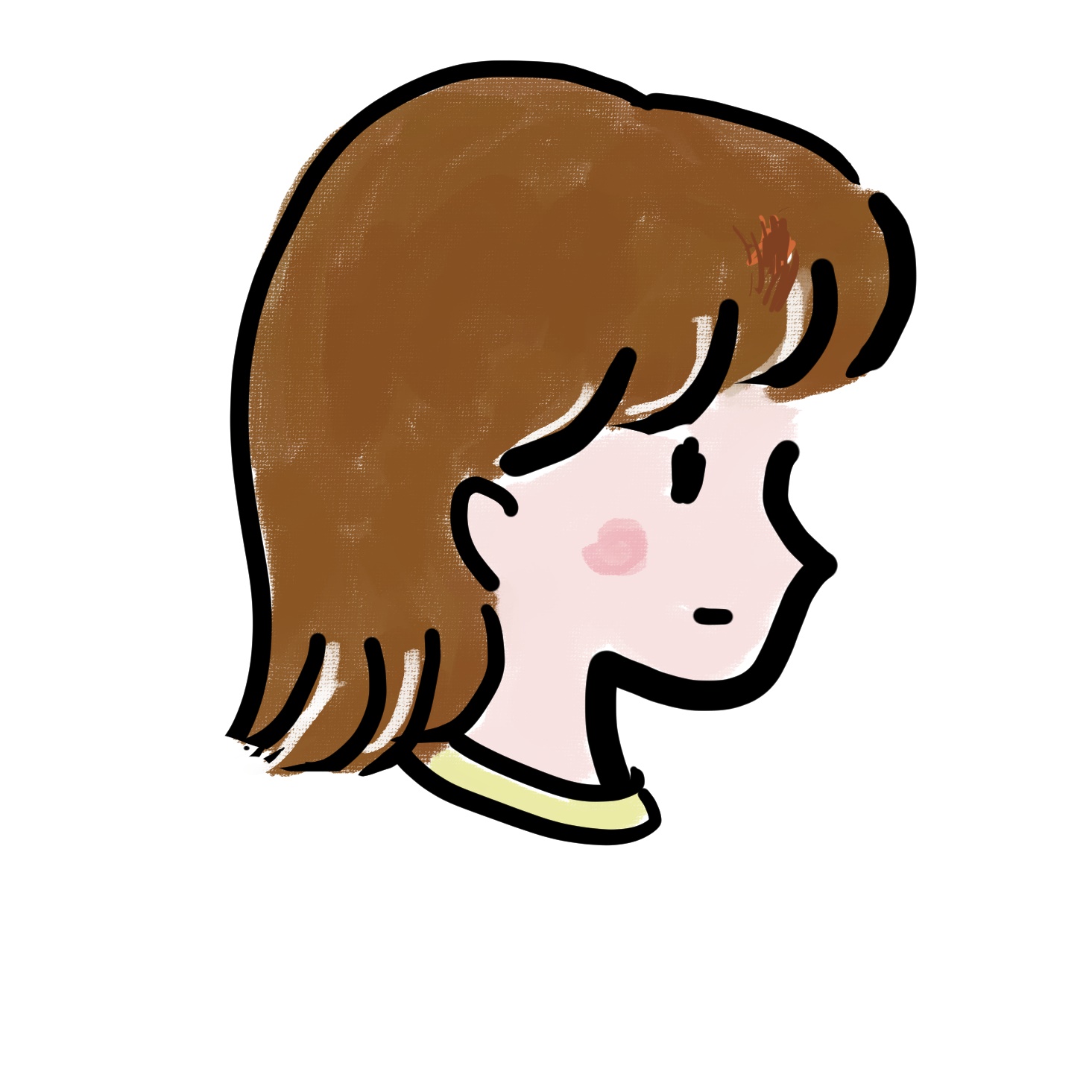

まとめ
“シュシュ女”の炎上と即特定をめぐる今回の騒動は、SNS社会が抱える大きな課題を浮き彫りにしました。
SNS特定班の手口は年々巧妙化し、もはや誰もが「特定される側」になりうる時代です。
背景や投稿、過去の言動がすべて“証拠”として積み上げられ、瞬く間に個人が晒されていく現実は、他人事ではありません。
特定に加担することで「正義を果たした」と感じるかもしれません。
しかし、それが本当に正しい行動だったのか、冷静に振り返る視点も必要です。
SNS上の“正義”や“スカッと感”が、人の人生を壊してしまう危うさを、私たちはもっと自覚すべきではないでしょうか。
炎上する側にも原因があるケースは多いものの、「晒して当然」という空気が当たり前になる社会は、誰にとっても生きづらいものです。
一線を越える前に、自分の言動が誰かを傷つけていないか、そして「次に晒されるのは自分かもしれない」という意識を、今一度持っておくことが、ネット時代を生きる私たちに求められているのかもしれません。
