
Xより
香港の街を歩くと、50階、70階の超高層ビルの外壁がまるでジャングルのように竹で覆われている光景を、今でも普通に見かけます。
そう、ビル建設の足場が竹製なのです。
「え、本当に竹で大丈夫なの!?」
初めて見る人は100%驚きます(笑)
でも2025年現在、この伝統は少しずつ終わりを迎えようとしています。
この記事では、
・なぜ香港だけ竹足場が生き残っていたのか
・日本で完全に消えた理由
・そして2025年はどうなっているか
を、わかりやすくお伝えします!
なぜ香港では足場に竹が使われているのか?

日経クロステック
香港ではなぜ足場に竹が使われているのでしょうか?
主な理由は、次の4つです。
1.めちゃくちゃ高度な職人技術がある
竹足場を組む「棚仔(たんちゃい)」は国家資格級の専門職。
複雑な形状のビルでもピタッと隙間なく組めるのは世界でもここだけ。
2.竹の「しなり」が台風に強い
硬い鉄は強風でポキッと折れることがありますが、竹はしなって衝撃を逃がす。
台風銀座の香港では、むしろ理にかなっていたのです。
3.軽くて安い
1本10〜15kg程度で人力で運べる+広東省産の毛竹が激安。
狭い路地裏の改修工事では今でも最強コスパ。
4.結束が超強力
竹の節にナイロンロープが食い込むので、見た目よりガッチリ固定されます。
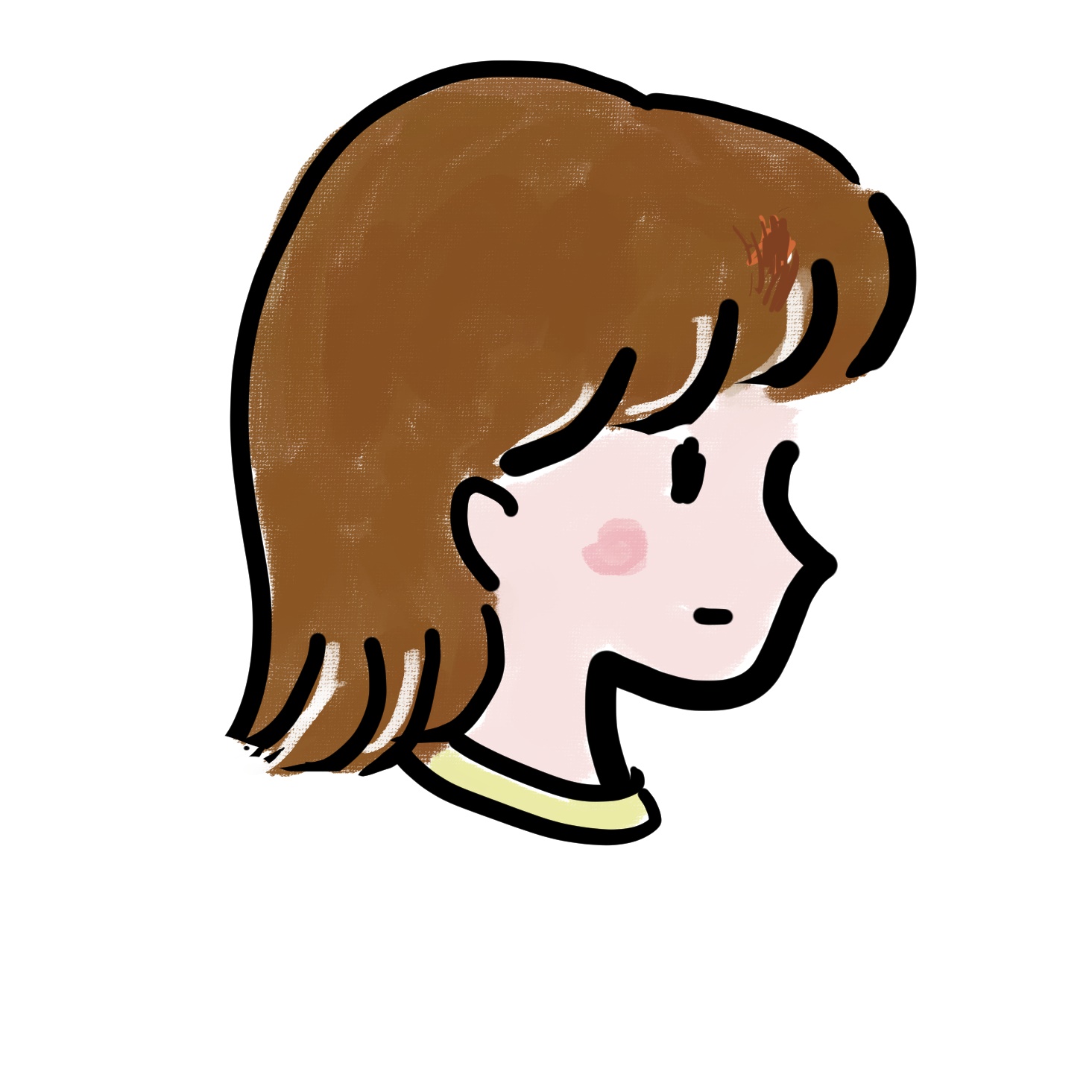
合理的だったから残っていたんだね
2025年は竹の足場の大きな転換点
2025年11月現在、香港政府は竹足場のフェーズアウト(段階的廃止)を本格化させています。
きっかけは2025年3月以降の規制強化と、特に11月に起きた香港北部のタイポ(Tai Po)地域の「Wang Fuk Court(ウォンフックコート)住宅火災」です。

毎日経済
改修中の竹足場が火の通り道となり、火災が急速に広がり、36人以上が亡くなる大惨事になりました。
これを受けて政府は
・民間でも40m(約14階)以上は金属orハイブリッド必須
というルールをさらに厳格化。
2026年以降は、ほぼ全ての高層工事で竹が姿を消す可能性が高まっています。

日本で竹足場が消えた理由
日本では1960年代後半〜1970年代に竹がほぼ絶滅しました。理由はシンプル。
・労働安全衛生法で強度計算・検査が義務 → 自然素材はデータが出せない
・万一の事故で億単位の賠償リスク → 元請けが絶対使いたがらない
・人件費が高すぎて手組みは割に合わない
・湿気が多くて竹がすぐカビる・腐る
今は鉄製システム足場が標準で、クレーンで数日で組み上げられます。
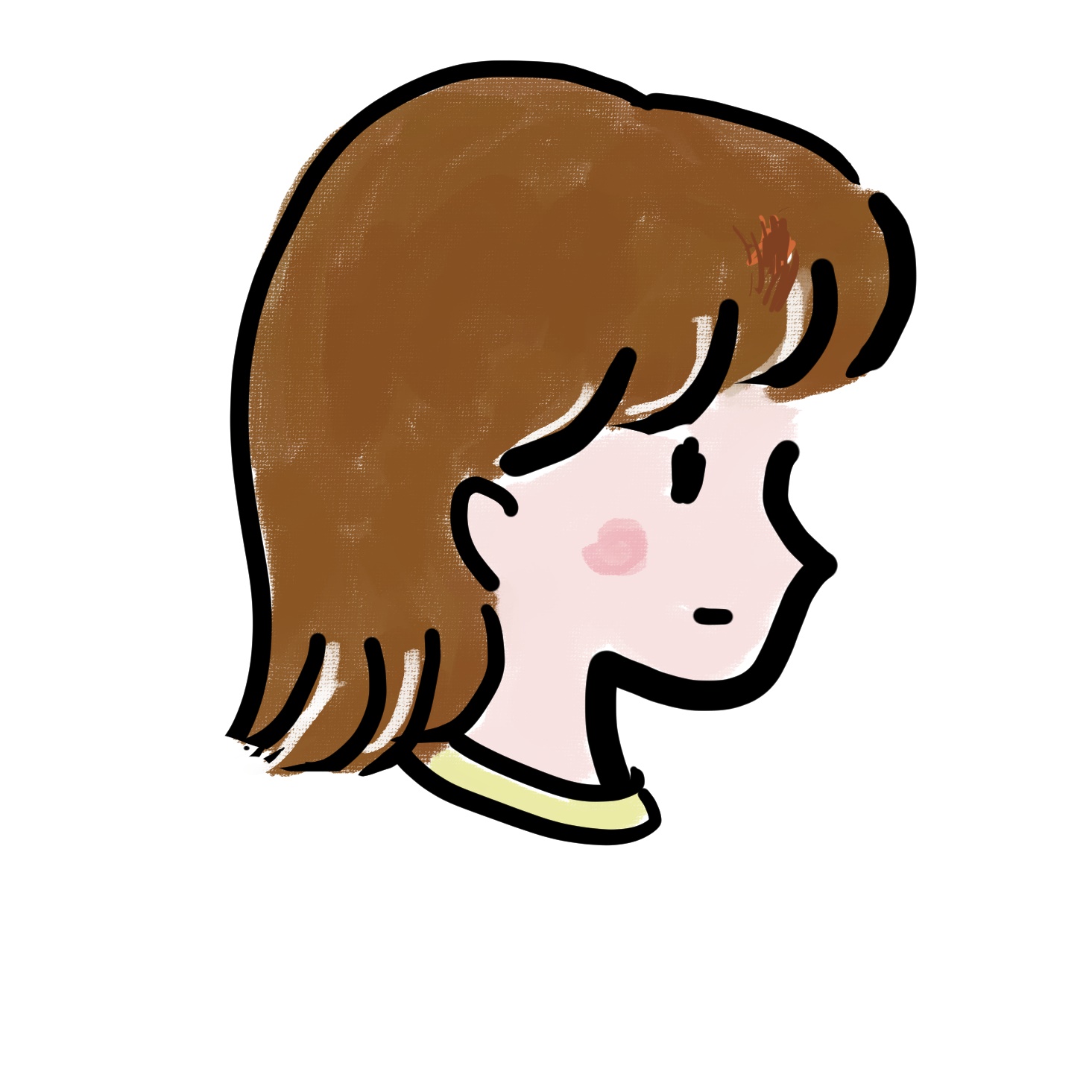
日本で竹製の足場なんて見たことないよ
でも日本にも、ほんの少しだけ竹の足場が残っている場所が…
国宝・重要文化財のお寺や神社の大修理では、「伝統工法再現」や「見た目の美しさ」のため、今でも竹足場が組まれることがあります。
例:
奈良・東大寺大仏殿周辺の修復(2020年代も使用実績あり)
京都の神社・寺院の屋根工事

2017年 清水寺屋根の大改修/ togetter

まとめ
竹足場の香港と日本の違いを見てみましょう。
・伝統+合理性で2020年代まで現役
・台風に強いしなりが武器
・2025年の火災で終焉が近づく
・安全+効率優先で1970年代に撤退
・湿気と法規制で不向き
・文化財修理で細々と生き残る
竹足場は「古い=ダメ」ではなく、環境や社会のルールにめちゃくちゃ左右される技術だった、という良い教材なんです。
もし今後香港に行く機会があれば、ビルの上の方をぜひ見てみてください。
もうすぐ見られなくなるかもしれない、「生きていた伝統技術の最後の輝き」がそこにあります。
そして日本に戻ってきたら、お寺の修復現場でひっそり組まれる竹足場を探してみるのも楽しいですよ。
